電気の仕事をするなら、まずは基礎の理解が欠かせません。
特に「電流」「電圧」、そしてそれを結びつける「オームの法則」は、どんな現場でも必須の知識です。
この記事では、現場でよく出てくる200V・400Vの話も交えながら解説していきます。
電流とは?
電流とは、電気が流れる量のことを指します。
単位は「A(アンペア)」で表され、配線やブレーカーを選ぶときに直結します。
例えば14sqのケーブルでどれくらい流せるか、20Aブレーカーならどこまで許容できるか、といった判断に必須です。
「とりあえず電気が流れてる」ではなく、数値として理解しておくことが大事です。
電圧とは?
電圧とは、電気を押し出す力のことです。
単位は「V(ボルト)」で表されます。
現場では100V(単相)、200V(三相やエアコン)、400V(三相モーターや大きな設備)などがよく使われます。
「同じ機械でも100V仕様か200V仕様かで性能が違う」なんてこともあるので、電圧を正しく理解することは非常に重要です。
抵抗とは?
抵抗とは、電気の流れを邪魔する性質のことです。
単位は「Ω(オーム)」で表されます。
例えば細いホースで水を流すと水の勢いが弱まるように、配線が長かったり細かったりすると抵抗が増えて電流の流れが弱まります。
現場では、ヒーターやモーターそのものが「抵抗」として働きます。
抵抗があることで電気が熱や動力に変換され、私たちは家電や機械を使えるわけです。
抵抗が小さすぎると一気に大電流が流れて危険ですし、大きすぎるとほとんど電流が流れません。
「電流と電圧のバランスを決める要素」として抵抗を理解しておくと、オームの法則がぐっとわかりやすくなります。
オームの法則とは?
ここまでの「電圧」「電流」「抵抗」を結びつける公式が、オームの法則です。
V = I × R
- V:電圧(ボルト)
- I:電流(アンペア)
- R:抵抗(オーム)
例えば、抵抗5Ωのヒーターに200Vをかけると、
I = V ÷ R = 200 ÷ 5 = 40A の電流が流れます。
この計算ができると、配線が焼けないか・ブレーカーは何A必要か、といった安全面の判断に直結します。
現場ではとっさの計算力が役立つので、慣れておくと強いです。
まとめ
- 電流:流れる量(A)
- 電圧:押し出す力(V)
- 抵抗:流れを妨げる性質(Ω)
- オームの法則:V = I × R
現場では200Vや400Vの機器を扱うことも多く、これらを正しく理解していないと大きな事故につながります。
「なんとなく」ではなく、計算で根拠を持って判断できるようにしておくことが大切です。
まずは基礎を押さえて、そこから配線の選び方やブレーカーの定格選定など、さらに実践的な知識につなげていきましょう。

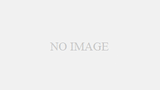
コメント